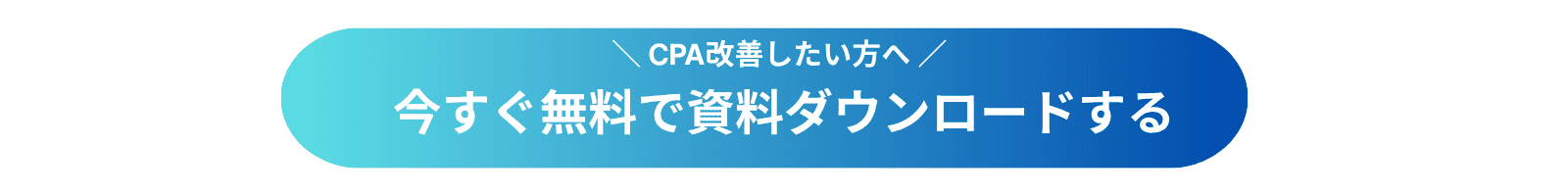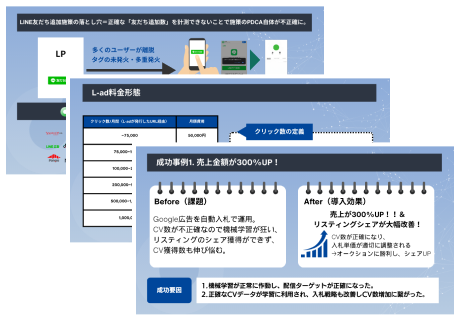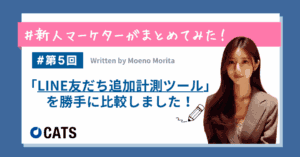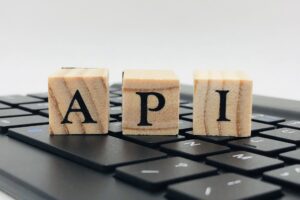Cookieに同意しないと見れない設計は可能?企業側が注意することを解説
最近、「Cookieに同意しないとサイトを見れない」ページが増えています。
Cookieは、ユーザーの操作情報や設定を保存してサイトを便利に動かす技術ですが、行動履歴の追跡や広告最適化にも使われるため、世界的に規制が強化されています。
日本でも、改正個人情報保護法や電気通信事業法の施行により、Cookieを利用する際の「同意」のあり方が問われています。
本記事では、「Cookieに同意しないと見れない」設計が生まれた背景と法的リスクを整理し、マーケティング担当者が実務で注意すべきポイントを具体的に解説します。
Index
1. Cookieとは?
1-1. Cookieがしていること
1-2. Cookieの種類
1-3. Cookieが問題視される理由
2. Cookieに同意しないとサイトを見れない仕様にする主な理由
2-2. ブラウザや分析ツールがCookie利用を制限しているから
2-3. 広告最適化や分析の精度を維持するため
3-1. 技術的には「できる」けど、法律的には危険
3-2. 日本ではグレーゾーン、海外では明確にNG
4-1. 改正個人情報保護法(2022年4月施行)
4-2. 改正電気通信事業法(2023年6月施行)
4-3. 総務省・個人情報保護委員会の見解
5. マーケティング担当者がCookie規制で注意すべきポイント
5-1. 同意は「自由意思」に基づかせる
5-3. Google・Meta広告など主要媒体の同意要件に注意
5-4. データの欠損を想定した分析設計を行う
6. まとめ
広告効果測定(計測)ツール
さまざまなWeb広告のクリック数とコンバージョン数が計測でき広告の最適化を実現する広告プラットフォーム。
広告の効果を媒体・クリエイティブ単位で正確に計測し、複数の広告効果を一元管理。
代理店用に管理画面を発行し商材評価ができるほか、媒体と直接連携しリアルタイムに広告成果を確認可能。
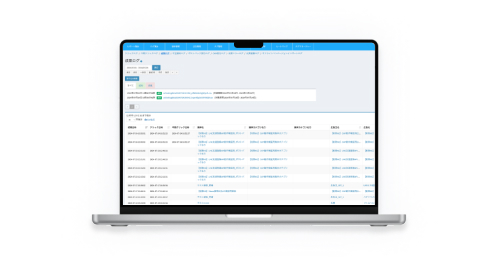
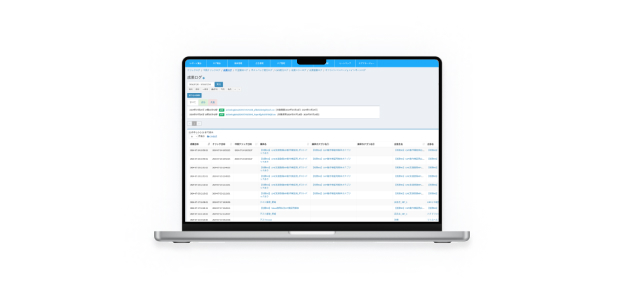
Cookieとは?

Cookie(クッキー)とは、ユーザーがウェブサイトを訪れた際に一時的に情報を保存する仕組みです。具体的には、サイトのログインIDや閲覧履歴、訪問回数、パスワードなどの情報をテキストファイル形式でユーザーのブラウザに保存します。
例えば、通販サイトで商品をカートに入れた後、ブラウザを閉じて再度アクセスしてもカートの中身が残っているのは、Cookieにその情報が保存されているためです。このようにCookieは、ユーザーの操作履歴や設定情報を一時保持し、ウェブ利用を便利にする役割を果たしています。
Cookieがしていること
Cookieが担っている主な役割は、大きく分けて2つあります。
1つ目はユーザーの利便性向上です。Cookieを使うことで、ウェブサイト上で入力したID・パスワードや言語設定などを保持でき、次回訪問時に再入力する手間を省けます。また前回の閲覧履歴をもとにおすすめのコンテンツや商品を表示できるため、ユーザーにとって快適な閲覧体験を提供します。
2つ目はサイト運営者側でのマーケティング活用です。Cookieによってユーザーが閲覧したページや時間帯などの行動履歴を収集すれば、サイト訪問者全体の傾向を分析できます。そのデータをマーケティング施策に活かすことで、ユーザーの興味・関心に沿ったコンテンツ配信や広告表示など、より効果的なアプローチが可能となります。
Cookieの種類
Cookieにはいくつか種類がありますが、代表的なのはファーストパーティCookieとサードパーティCookieの2種類です。
ファーストパーティCookieは、ユーザーが訪問しているそのウェブサイトのドメインから発行されるCookieです。ログイン状態の保持やカートの中身の維持など、訪問先サイトの機能向上に用いられます。
一方、サードパーティCookieはユーザーが閲覧中のサイトとは異なる第三者のドメインから発行されるCookieです。たとえば閲覧サイト上に表示される広告の提供元などが発行するもので、過去に検索した商品やサイトの情報をもとに別サイト上で関連広告が表示される場合に利用されています。
しかし近年の規制強化の中心となっているのは、特に第三者発行のサードパーティCookieです。こうしたCookieはユーザーの行動追跡やデータ共有に用いられ、プライバシー保護の観点から問題視されています。
Cookieが問題視される理由
Cookie自体は便利な仕組みですが、主にプライバシーの観点から問題視されるケースがあります。
特にサードパーティCookieは、ユーザーが意図しない形で複数のサイトにまたがる詳細な行動履歴を収集・共有できてしまいます。たとえばあるサイトで検索した内容に関連する広告が別のサイトやSNS上で次々に表示されるのは、サードパーティCookieによるクロスサイト追跡の結果です。
こうした過度な追跡はユーザーのプライバシー侵害につながるため、各国で規制が進む要因となりました。
またCookieには識別子としての役割があるため、匿名情報であっても蓄積・分析されることで個人の興味関心や属性が推測できてしまいます。さらに、他のデータと組み合わせれば個人を特定できてしまうリスクもあります。
このように「知らぬ間に自分の行動や情報が追跡されている」状況への懸念が高まり、Cookieは個人情報保護やプライバシー保護の面から問題視されるようになったのです。
Cookie規制をわかりやすく解説!LINEマーケティングに与える影響は?
Cookieに同意しないとサイトを見れない仕様にする主な理由

近年、多くのウェブサイトで「Cookieの利用に同意してください」というバナーが表示されます。その中には、ユーザーがCookie利用に同意しないとサイトの閲覧が制限されるケースも存在します。サイト運営者がこのような「同意しないと閲覧不可」仕様を採用する主な理由として、以下の点が挙げられます。
個人情報を含む可能性があるため同意が必要だから
Cookieに保存される情報は一見匿名の識別子ですが、組み合わせ次第では特定の個人に関するデータとなり得ます。
日本では2022年4月の改正個人情報保護法で、Cookie情報はそれ単体では個人を特定できなくとも「個人関連情報」として新たに位置付けられました。
個人関連情報とは、生存する個人に関する情報であって、氏名や住所といった「個人情報」には該当しないものを指します。Cookieはまさにその典型例であり、改正法では第三者に提供してその相手方で個人データとして取得される可能性がある場合には規制の対象となりました。
そのためサイトによっては、Cookieにユーザーのプライバシーに関わる情報が含まれる可能性を考慮し、事前に同意を求める必要があると判断しています。
特にCookieを用いて取得したデータを広告会社などの第三者と共有する場合、適切にユーザーの同意を得ておかないと法的リスクが生じ得ます。
ブラウザや分析ツールがCookie利用を制限しているから
もう一つの理由は、近年の技術的な環境変化です。
主要なブラウザ提供企業各社はプライバシー保護の流れを受け、ブラウザ側でサードパーティCookieの利用を段階的に制限・ブロックし始めています。
例えばSafariやFirefoxでは、ユーザーが特に許可しなくてもトラッキング目的のCookieは自動的にブロックされる設定が導入されています。その結果、ユーザーが同意しないままでもブラウザレベルでCookieが機能しない場合があり、サイト側ではユーザー行動の追跡やデータ取得が困難になります。
サイト運営者としては、Cookie利用に同意してもらうことでブラウザやツール側の制限を解除し、従来通りデータ収集・解析を行いたいという狙いがあります。
広告最適化や分析の精度を維持するため
Cookieの利用可否は、デジタルマーケティングの成果にも直結します。ユーザーにCookieを拒否されると、リターゲティング広告などでは適切な広告配信がしにくくなります。
例えば以前見ていた商品の広告を後日別サイトで表示するといった手法はサードパーティCookieに依存しているため、Cookie規制が強まるとそうした最適化が難しくなるのです。
また、コンバージョンに至るまでユーザーがどんな経路を辿ったか追跡できなくなり、広告や流入経路ごとの貢献度の計測精度も低下します。
このような広告配信の効率低下やアクセス解析データの欠損を防ぐために、あえて「Cookieに同意しなければコンテンツを利用できない」設計を取るサイトもあります。
Cookieに同意しないと見れない設計は可能?

技術的には「同意しないと見れない」設計が可能である一方で、法的・倫理的な側面から慎重な判断が求められます。ここでは、その可否とリスクの所在について掘り下げていきます。
技術的には「できる」けど、法律的には危険
結論から言えば、ユーザーがCookie利用に同意しない限りサイト閲覧そのものをさせない仕組みを技術的に実装すること自体は可能です。
実際に画面全体にポップアップを表示し、「同意する」ボタンを押さないと先に進めないようにしているサイトも存在します。しかし法律的にはこの手法は非常にグレーであり、海外では明確に違法と判断されるケースもあります。
なぜ危険かというと、個人情報保護の考え方において「同意」は本来自由意思に基づく必要があるからです。同意しなければサービスを使わせないというのは、ユーザーに事実上の強制をしている状態であり、真に自主的な同意とは認められない恐れがあります。
特にEUのGDPRでは、サービス提供の対価として包括的に同意を強要することは「自由な同意」とみなされず無効とされています。仮にこのようなCookieウォールを敷いてEU圏のユーザーにサービス提供を行えば、GDPR違反として巨額の制裁金対象となりかねません。
日本ではグレーゾーン、海外では明確にNG
日本においては、2025年現在Cookieバナーやダークパターンそのものを直接禁止する法律は存在しません。したがって形式的には「Cookie不同意なら閲覧不可」という設計自体を直ちに違法と断じる規定はない状況です。
しかし、だからといって安全というわけではありません。上述のように欧州ではCookieウォールは明確にNGとされていますし、日本国内でも2022年施行の改正個人情報保護法や2023年施行の改正電気通信事業法によって、結果的にこのような設計をとることがリスクとなる枠組みができています。
Cookieウォールの実装は技術的には可能でも法的・倫理的リスクが大きいのが現状です。海外では既に違法と判断されている点を踏まえると、国内向けサイトであっても安易に採用すべきではないでしょう。
Cookie規制をわかりやすく解説!LINEマーケティングに与える影響は?
Cookieに同意しないと見れない設計の法的リスク

「同意しなければ見せない」設計には法的なリスクも伴います。日本の法制度を中心に、具体的にどのような法律がCookieに関係しているのかを整理します。
改正個人情報保護法(2022年4月施行)
2022年4月に施行された改正個人情報保護法では、Cookieなど従来「個人情報」に該当しない識別子について新たに「個人関連情報」という概念が導入されました
Cookie IDや閲覧履歴、端末の識別子がこれに当たります。個人関連情報そのものは氏名や住所のような個人情報ではありませんが、特定の個人に関する情報であることに変わりはないため法規制の対象に含められた形です。
改正法では、個人関連情報を第三者に提供し、提供先でそれが個人データとして利用される可能性がある場合には制限が課されました。具体的には、提供先企業(第三者)がユーザー本人から同意を取得していることを確認できなければ、その個人関連情報を提供してはならない旨が定められています。
このように改正個人情報保護法の下では、Cookie情報の第三者提供にあたってユーザーの同意取得が事実上求められる場面があります。ユーザーがCookie利用に同意しないにもかかわらず無理に提供を続ければ、同法違反となるリスクがあります。
改正電気通信事業法(2023年6月施行)
2023年6月16日施行の改正電気通信事業法では、インターネット上のサービス提供事業者に対し新たな「外部送信規律」が導入されました。
これは「日本版Cookie規制」とも称されるもので、ウェブやアプリを通じてユーザーの端末から情報を外部に送信する行為に一定のルールを課すものです。対象となる事業者は幅広く、必ずしも従来の電気通信事業者に限らず多くのウェブサービス運営者がこの規律に従う必要があります。
外部送信規律の内容は大きく、ユーザーから取得した情報を第三者に送信する際に事前に通知・公表すべき事項を定め、必要な場合はユーザーの同意取得や拒否権の機会提供を求める点にあります。
具体的には、ユーザー端末に記録された利用者情報を外部に送信するプログラムを実装している場合、その送信される情報の内容や送信先、利用目的をあらかじめユーザーに分かりやすく知らせる必要があります。その上で、一定の場合にはユーザー本人の同意を得たり、もしくは後から拒否できるようにしたりする措置が求められます。
総務省・個人情報保護委員会の見解
Cookie規制に関しては所管官庁である総務省と個人情報保護委員会も見解を示しています。個人情報保護委員会のFAQでは、Cookieなど端末識別子について「それ単体では個人情報に該当しないが、生存する個人に関する情報であり個人関連情報に該当する」と明記されています。
さらに「他の情報と容易に照合することにより特定の個人を識別できる場合には、Cookie情報も合わせて個人情報として扱われる」と述べられており、Cookieデータも状況次第で厳格な個人情報とみなされることが確認されています。これはつまり、企業はCookieだからといって安心せず、個人情報に準ずる慎重さをもって取り扱うべきだという委員会の考えを示唆します。
マーケティング担当者がCookie規制で注意すべきポイント

Cookieを活用するマーケティング施策には、法令遵守だけでなくユーザーの信頼を得る姿勢も不可欠です。ここでは、担当者が具体的に注意すべき観点をいくつか紹介します。
同意は「自由意思」に基づかせる
ユーザーから取得するCookie同意は、必ずユーザー本人の自由な意思決定に基づく形にしなければなりません。サービスを利用するために同意を強要したり、同意しない選択肢を極端にわかりにくくしたりすることは避けるべきです。
ユーザーが自発的に判断し、同意する・しないを等しく選べる環境を用意することが、法的にも倫理的にも求められるのです。
これはユーザーとの信頼関係構築にもつながり、長期的に見れば企業のブランド価値向上にも寄与するでしょう。
「Cookieの利用目的」を明確かつ具体的に書く
ユーザーに同意を求める際には、Cookieを何の目的で利用するのかをできるだけ明確かつ具体的に伝える必要があります。
例えば、「ログイン情報の保持」「閲覧履歴に基づく商品レコメンド表示」「アクセス解析によるサイト改善」「第三者配信による広告のパーソナライズ」といった具合に、Cookieでどんなデータを取得し何に使うのか具体的に説明しましょう。
また、その説明はユーザーにとって分かりやすい平易な言葉で書くことが重要です。専門用語だらけのプライバシーポリシーにリンクするだけでは、多くのユーザーは内容を理解できません。同意バナー上やポリシー上でも、ポイントをかみ砕いて記載する工夫が求められます。
Google・Meta広告など主要媒体の同意要件に注意
デジタルマーケティング担当者であれば、GoogleやMetaなど主要プラットフォームが定めるプライバシーポリシーや利用規約にも注意を払う必要があります。これらのプラットフォームは各国の法規制に合わせ、広告配信や解析サービス利用時のデータ取り扱い要件を設けています。
例えばGoogleでは、自社の広告サービスと連携して企業から受け取ったCookie等の情報をGoogle側で個人データと結び付ける場合、Google自身がユーザーから必要な同意を取得すると明言しています。
逆に言えば、企業側がGoogleのCookie IDなどを自社の持つ個人データと統合する場合、法律で義務付けられたユーザー同意を取得していなければ禁止するとポリシーで定めています。
データの欠損を想定した分析設計を行う
Cookie規制が進む現在、ユーザーの一部からデータが取得できないことを前提にウェブ解析や広告測定を設計する必要があります。
例えば昨今では、一定割合のユーザーがCookie利用を拒否したりブラウザ側でブロックされたりするため、従来通りのトラッキングが通用しないケースが増えています。その結果、サイト流入経路やユーザー行動のデータが部分的に欠落し、コンバージョンまでの経路分析に不確実性が生じます。
マーケティング担当者は、この「データ欠損」を織り込んでKPI設計や分析を行わなければなりません。具体的な対策としては、以下のようなものが考えられます。
モデル化・推計による補完
取得できたデータから統計的に欠測部分を推定し、全体傾向を分析する。
ファーストパーティデータの活用
会員ログイン情報や自社アプリのデータなど、比較的ユーザー同意が得やすく継続取得可能な自社保有データを重視する。
サーバーサイド計測への移行
ブラウザ側の制限を受けにくいサーバーサイドのトラッキング手法やコンバージョンAPIを導入し、計測精度を補完する。
重要指標の見直し
ユーザー行動を細かく追跡できない前提で、ページビュー数やクリック率といった定量指標だけでなく、アンケートやユーザーテストによる定性指標も組み合わせて評価する。
海外アクセスを想定した場合はGDPR準拠が必須
自社サイトが海外(特にEU圏)のユーザーからアクセスされる可能性がある場合、GDPRをはじめとする各国のデータ保護法規制を無視できません。
GDPR下では、ユーザーのプライバシーに関わるCookie利用には原則として事前の明示的な同意が必要です。たとえ日本企業でも、EU居住者にサービスを提供したりサイト閲覧させたりする場合にはGDPRが適用されるため、「同意なくCookieを設置しない」「同意撤回をいつでも受け付ける」などの厳格な運用が求められます。
GDPR準拠の運用をしておけば日本国内の規制にも自然と適合するケースが多いため、先手を打ってグローバル基準で対応しておくことが望ましいでしょう。
まとめ
Cookieはユーザーの利便性向上やマーケティングデータの収集に欠かせない反面、個人情報やプライバシーに関わる課題から世界的に規制強化の流れが進んでいます。
海外で始まったCookie規制の動きは日本でも徐々に加速しており、特にサードパーティCookieは今後数年以内に廃止されていく方向です。2022年の改正個人情報保護法や2023年の改正電気通信事業法施行により、日本企業もCookieを巡る法的ルールを無視できなくなりました。
適切なCookie運用ポリシーを整備し、プライバシーとマーケティングの両立を図ることで、これからのウェブ戦略において競争優位性を築いていきましょう。

Contact
マーケティングにお悩みの方は
お気軽にご相談ください